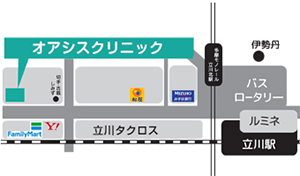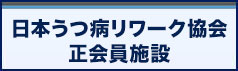平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。このページではその概要をご紹介いたします。
通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
なお一定所得以上の世帯*1(区市町村民税所得割23万5千円以上)で受診者が「重度かつ継続」に該当する場合、現在は自立支援医療の支給対象(月額上限2万円)となっております。
これは国が令和3年3月31日(※平成30年3月31日から延長となりました)までの経過措置として定めたものです。
*1「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方です。
お住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください (担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。
自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した 医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割 の自己負担となります)。
申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付 されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関 や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
なお、受給者証と管理費票が届くのに申請後、約1ヶ月ほどかかります。
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
なお、一定所得以上の世帯の方については、現在のところ令和3年3月31日までの経過措置となっています。
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。
所得に応じて負担の上限額が設定されています。
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 受診される方の 収入が 80万円以下 ↓ 医療費の1割 負担上限額 月額2500円 |
左記以外の 市町村民税 非課税世帯 ↓ 医療費の1割 負担上限額 月額5000円 |
市町村民税 3万3千円未満 |
市町村民税 3万3千円以上 23万5千円未満 |
市町村民税 23万5千円以上 |
| 医療費の1割 | 制度 | ||||
| (医療保険の自己負担上限額まで)※3 | 対象外※4 | ||||
| 重度かつ継続の該当者※2 | |||||
| 負担上限額 月額 5000円 |
負担上限額 月額10000円 |
負担上限額 額20000円 平成30年3月31日までの経過措置 |
|||
※2 重度かつ継続:
詳細情報に関しましては、東京都福祉保健局の自立支援医療(精神通院医療)のページをご覧ください。